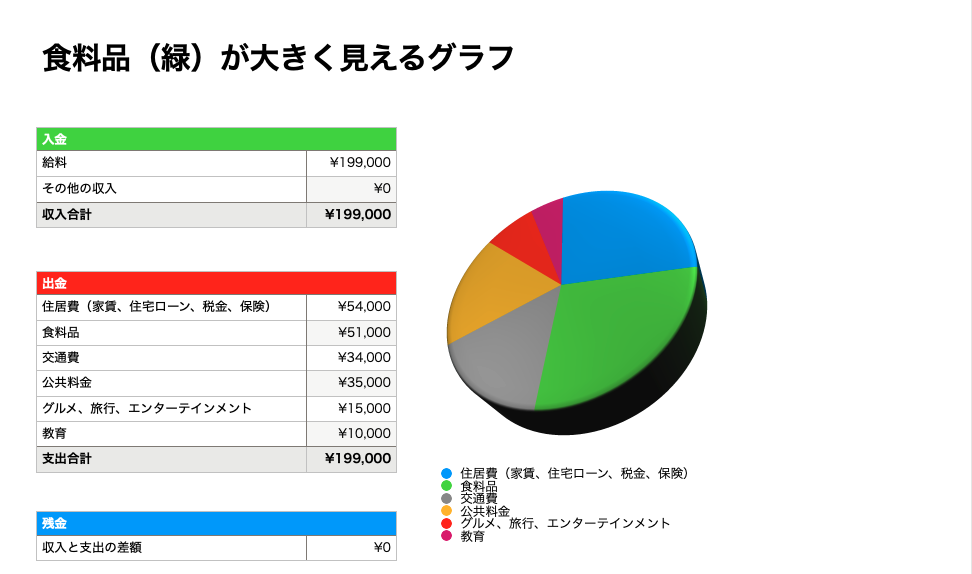統計のトリック
因果と相関
ふと、気になることがあって、一見関係のない二つの事柄に注目して調べてみると、相関関係を見つけることがある。例えばゲームに熱中しているこどもたちは、学校の成績に何らかの影響があるとかね。そうしてお役所や学者はそれを誠実に調べたりする。すると、想定していた通りに、ゲームに夢中になるこどもは、おおよそ学校の成績が悪いという結果になる。やっぱりゲームは成績を下げる要因になっていると結論づけたりするね。それを聞いた人々の反応は様々だけど、総じてゲームばっかりしているこどもたちに一言もの申したいという欲望と合致するので、意外とすんなりと受け入れてしまうんじゃないかな。で、いつの間にかそれが因果関係とすり替えられる。ゲームする時間さえ奪ってしまえば成績が良くなると信じて疑わない。本来なら相関が見つかった事象以外に、必ず他の事柄が潜んでいるんじゃないかとチェックする必要があるのにね。相関関係と因果関係の基本的な成立条件をまるで無視しているよ。
統計的研究の罠
統計上に出た結果をもって、これを「科学的根拠」とか「研究成果」として無批判にうやうやしく崇めてしまう。今時は「エビデンス」なんて横文字でわざわざ言うことでさらに煙に巻く傾向が強いね。特によくわからないことに対しては、無条件に信じる傾向が強いみたい。単に異なる事象の相関関係が因果関係にすり替わって、世の中の常識や根拠となって不当にこどもたちを苦しめることになってしまう。成績が悪いことと、ゲーム好きなことには因果関係は成立しない。ここまで説明しても、もはや聞く耳もたない人が多いね。それこそきちんと教えるべきことなんだけど、それを見破るほどの教養がある人が多くなると誰かがやりにくくなるので、わざとそこはできるだけ教えないようにしているのかしら。もやもやしているけどうまく反論できない、ゲーム好きなこどもたちの味方になる誠実な大人はもっとたくさんいてもいいと思うんだけどね。
詐欺師は数字を使う
数字は嘘をつかない。数字の結果こそがよりどころにすべきこと。それには反論しにくいね。個人的な感情やなんとなくそう思っているとかでは数字に勝てるわけがない。それはしっかりとそう教えられている。だからグラフとか数字とか専門用語が出てくると思考停止してしまうね。その部分での教育は実に優秀で行き届いているから、なんだかよくわからない相関関係の結果で人々を操ることができるんだね。そうやってうまく人々の行動をコントロールするためには、どんな数値をもっともらしくだせばいいかということと、多くの人がなんとなく感じているところとをマッチさせれば、まんまと騙すことに成功っていうシナリオが成立するんだよ。今、世の中で喧伝されている関係性には、せめて相関があっても因果関係は見られないとか、その他の要素が隠れているかどうかのチェックをきちんと説明しなければいけないと思うけど。特にプロや専門家は特にね。
自分の頭で考える
先のゲーム時間と成績の相関関係もそうだけど、ゲームをする時間が長いから勉強する時間が短くなるという相関があったとして、成績が芳しくないということには直結しないのは、こどもたちの言い分を聞けばわかるはずだよね。そもそも勉強が楽しくないからしないだけで、ゲームしなくなったからといって、よかった、ようやく勉強する時間が取れるようになって幸せ、とはならないのは明白だよね。相関関係をエビデンスにするのなら、そうやって次はどうして勉強に興味関心が持てないのか、という事象を洗い出して調査を進めていかないとなんとも結論がでないね。要するに、言いたいことや押し付けたいことが先にあって、それに都合のよい相関関係を因果関係のように絶対視させたいだけなんだよね。それで世の中をコントロールしたいわけ。そんな世の中だけど、そんな罠にひっかからないように心穏やかに過ごす秘訣は、自分の頭でしっかりと考えてみるということ。一番大切なのはそのことを伝えていくことじゃないのかな。いい大人がいま、連日連夜いろんな相関を調べる研究結果の報道に振り回されている現状をみると、そこが一番足りないところだと感じるんだけど。どう思う?